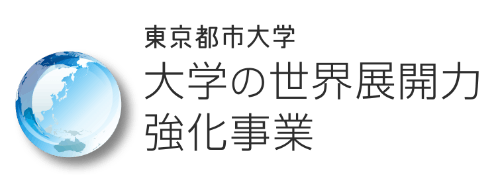JDパイロットプログラム派遣者レポート(2023年度派遣・5名)
パイロットプログラム レポート
理工学部 応用化学学科学科 3年 Iさん
こんにちは。 6週間のオーストラリアでのプログラムを終え、無事に帰国することができたので、今回のプログラムで感じた事、学んだこと、日本と海外の違いなどを報告したいと思います。 私は昨年TAPにも参加しているので、その時の経験との違いなども踏まえてお伝えしたいと思います。
パイロットプログラムに参加した私たちはMEXT studentsと呼ばれており、MEXTはMinistry of Education, Culture, Sports, Science and Technologyの略で、文部科学省の意味です。私たちはTCU、ECU、そして文部科学省のサポートがあることで、このプログラムに参加することができたのでこれらの支援にとても感謝しています。
まず、行きのフライトについて、昨年はシドニーで乗り換えましたが、今年はシンガポールで乗り換えました、シンガポール乗り換えの方が短く感じ、疲れにくかったように思うのでおすすめです。また、シンガポール空港はとても綺麗で、ぜひ今度シンガポールにもいきたいと思いました。
およそ8ヶ月ぶりに戻ってきたパース空港に着いた時は、懐かしさが込み上げました。オーストラリアのカラスの鳴き声は独特で、赤ちゃんのような鳴き声がするので、その声を聞いた時に「あ、パースに帰ってきた」という気持ちになりました。
人生の初のホームステイ先は、仏教徒のベトナム人のお母さんと、オーストラリア人のお父さんの家で、二階建ての日本風の家でした。初日は癖が強すぎるホストマザーの英語がほとんど聞き取れず、この先41日の生活に不安を感じていましたが、3日程で90%程度理解できるまでに慣れることができました。ホストマザーは40年ほどオーストラリアに住んでいるにもかかわらず英語があまり得意ではないようで、発音や文法的によくわからないことがあり意思疎通に苦労しましたが、向こうもまた、私の英語が理解できないと言っている場面が多々ありました。私の英語はかなりAmerican Englishで聞きやすい方だったかと思いますが、ベトナム人独特の聞き返し(あ”ぁん?はぁぁ!?のような日本人にとっては怖い響きですが彼らにとっては「え、なに?」と同じようなもの)をされる度に心が折れました。ホストマザーは、ものすごくAussieなEnglishを話すホストファザーとはコミュニケーションが取れているようでしたが、それでも終始怒っているようなトーンで、ホストファザーの心の広さを感じました。また、ネイティブはノンネイティブの英語を聞き取る能力や理解する能力が高いですが、一方でノンネイティブとノンネイティブの会話の場合、互いに癖のある英語を話す場合が多く、そのアクセントに慣れていないため意思疎通の壁が大きいと感じました。
ホームステイでは一部屋と3食を提供すれば良い決まりになっていましたが、一緒に渡航して他のメンバーのホストファミリーはお菓子やジュースを買ってもらっていたり、車で送り迎えをしてもらったり、洗濯や掃除をしてもらったり、一緒に映画やショッピングに連れて行ってもらっており、本当の家族のようにホストしてもらっていました。しかし、私のホストマザーは恐ろしいほどお金にシビアで、毎日これはいくらで買ったんだ、これは高かったけど健康にいいものなんだ、という話をされ、夜ご飯に出てきたVietnamese hamを指してこれ高いんだよ、と言ってくるような人でした。滞在2日目には近くのショッピングセンターへ連れていかれ、洗濯洗剤やバスタオル、ボディーソープやハンドソープも自分で使うなら自分で買うんでしょ?と自腹で購入させられました。また、私は滞在中に「ヨーグルト問題」というものを抱えており、これは毎朝ヨーグルトとグラノーラを食べて生きてきた私が、ホストマザーにヨーグルトが食べたい、と伝えたところ、私たちの用意したのもの(ハムチーズトースト)を食べないなら自分で買ってきなさい、と言われ、結構な額の滞在費を払っているにも関わらず、私に全く投資してくれないというものでした。これは朝ごはんのみならず、夜ご飯を大量に作るホストマザーは、前日の夜ご飯をタッパーに詰めて次の日の昼食に持って行きなさいと言うのですが、それが消費しきらない時は夕飯、昼食、夕飯昼食と全て同じものを食べなくてはなりませんでした。たまにおかずがなくなった時は、昼ご飯がスパムと白米だけの日もありました。昨年ECU village(寮)に住んでいたときは自炊だったため自分で食材を買うことに不満はなく、楽しんで自炊しており、今回の食生活が嫌になったこともしばしばありました。しかし、美味しいベトナムのヌードルスープが夜ご飯になることもあり、アジア料理をあまり食べない私にとっては新鮮で、貴重な機会でした。
そんな私も、一度だけホストマザーと出かけたことがあります。ある日、来週の土曜日にピナクルズツアーへ家族で参加するから一緒に行くか、と誘ってくれたのです。昨年はタイミングが合わず行けなかったピナクルズに、通常100ドル以上するツアーが70ドルで参加できると言うので一緒にいくことにしましたが、当日、頼みのホストファザーは仕事があって一緒にいけないことが判明し、さらにその格安ツアーはベトナム語ツアーだったのです。完全に英語のツアーだと思っていた私は、狭くて小さなバスにぎゅうぎゅうに詰め込まれたベトナム人の中で疎外感を感じました。また、彼らは(他国の人に比べ)大声で話し、屋外コンサート並みの爆音でベトナム音楽をバスの中でかけ始めました。私は寝ようにも寝られず、騒音で耳が痛くなり、誰とも話せない孤独感から泣き出しそうになりました。片道 4時間半かけてたどり着いたピナクルズでは、ホストマザーは自分のお姉さんや友達と写真を撮り、私のことはほったらかしでした。家族やカップルで来ている他のベトナム人に声をかける気も失せ、私は1人、岩の間にスマホを置いて自撮りをしていました。帰り道にはtwo rocksという謎の岩を見るために停車し、その後ビーチに行くと聞いていましたが、ビーチには寄らず出発地点に帰ってきました。ピナクルズ自体は神秘的で非常に興味深い場所でしたが、この日は私の人生の中で最も過酷で最悪な日だったと言っても過言ではないほどインパクトのある日でした。しかし、このような機会がないとベトナム人のカルチャーに触れる機会はなかったと思いますし、日本で生まれ育った私の「あたりまえ」は、違う国の人々にとっては全く「あたりまえ」ではなく、彼らにとっての「あたりまえ」も又、私にとっては馴染みのないものであるということ、それが「異文化交流」をするということであると思いますし、それこそが留学して新しい文化に触れるという一つの醍醐味であると感じました。このピナクルズツアーで感じた孤独感は、日本に来た外国人の方々の気持ちに置き換える事もできると感じ、全くわからない言語の中に飛び込んで孤独を感じている人がいれば、 積極的に手を差し伸べたいと思うようになりました。
私の家には6人のブータン人が部屋を借りて住んでおり、向かいの家(ホストファミリーが昔住んでいたらしいお家)にも10人ほどのブータン人が住んでいました。彼らはとても優しく親切な人が多く、自分たちが作った夕食を私に分けてくれたり、部屋で行われた誕生日会に呼んでくれたりもしました。1人のハモという女の子が作ってくれたホワイトカレーがとても美味しかったので、もう食べられないと思うととても恋しいです。彼らはとても辛いものを食べるため、帰国当日の昼に「Do you wanna have lunch with me? It’s not spicy, just a little spicy.」と言って骨付きチキンを料理していたブータン人の1人にお昼ご飯を分けていただいたのですが、私が人生で食べた中で1 番辛い料理でした。でもとても美味しかったので唇が腫れながらも完食しました。ブータンの公用語はズォンカというもので、なかなか聞く機会はないと思いますが、私は街でズォンカを話している人がいると、「あ、ブータン人だ」と判別できるまでにリスニング力が上がりました(意味はわかりません)。ちなみに、今回のプログラムに参加した5人のうち3人の生徒は中国人だったため、日常的に彼らが中国語を話しているのを聞いていた影響で中国語も判別できるようになり、ホストマザーが毎晩誰かと大声で電話しているのを聞いていたため、ベトナム語も判別できるようになりました。つまり今回私は、日本語、英語、中国語、ベトナム語、ズォンカ、の5ヶ国語に毎日ふれ、これらの言語を聞き分けることができるようになり、音の特徴も掴むことができました。昨年のTAPでは皆が英語を話し、TAP 生同士では日本語を話すことも多かったため、常に触れていた言語は2つでした。意味を理解できるようになった訳ではありませんが、これだけ多くの言語に日常的に触れながら生活する機会は、もうなかなか訪れない貴重な機会であったと感じます。
ECUでの英語のクラス、ECCもまた、非常にインターナショナルなクラスでした。昨年私が参加していたAE5という最上位レベルの英語クラスには、日本人のTAP 生が16人と途 中から参加したブータン人が1人だけでした。海外の授業に参加するのが初めてだった私はもっとたくさんの留学生が、さまざまなホームカントリーから参加している様子を想像していましたが、実際はほぼ日本人で少しがっかりした記憶があります。(もちろん授業は楽しく、英語力も伸びましたが。)一方で今回のAE4には日本人が2人、中国人が5人(内3人TCU 生)、ブータン人が2人、ベトナム人が2人、イラン人が3人、アフリカから1人、が参加していました。みんな授業に非常に積極的で、優しく思いやりのある人たちでした。自分の意見をはっきり言うことが必ずしもいいと思われない日本と違い、自分の意見を伝えた上で「あなたはどう思う?」と他の人に意見を聞いたり、それをしっかり聞いた上で同意を示すような彼らの授業スタイルは私にとってとても居心地の良いものでした。先生方はとても優しくプロフェッショナルで、生徒が積極的に手を挙げられるような雰囲気で授業を進めてくれました。的を得ていないような発言をしたときも、決して邪険には扱わず、 親身になって話を聞いてくれました。これは生徒にとって安心感につながり、積極性の向上つながると思いました。日本の授業では周りの人に合わせたり、先生の授業を静かに聞いているのが良い生徒の象徴である気がしますが、本来、生徒の学びを深めるには主体的に授業に参加し、積極的に発言することが好ましいと思います。ECCで学んだ時間は本当に楽しい時間だったので、本来10 週間の英語プログラムを5 週間で去らなければならないのは非常に残念でした。AE5とAE4の違いとしては、AE5の方がレベルが高く、非常にアカデミックなスキルが求められるため、当時学部 2年生だった私にはかなりハードな内容でしたが、AE4はアカデミックな内容を扱いつつも、文法や一般的な背景知識を扱うことも多く、 自分のレベルに合っていると感じました。ここで学んだ知識は、将来自分が学術論文を書くときや読むとき、もしかしたら海外の大学で学ぶことになったときに必ず役にたつと確信しています。
もう一つTAPと大きく違う点は、Joondalup campusへ訪問し、ラボ見学をしたりECUで何が学べるか、ということについて学ぶ機会が滞在期間中に2回あったことです。昨年は個人的に友人たちと2回訪問したのですが、1回目はオクトーバーフェスタの時で、2回目はハロウィーンパーティーの時だったため、学業とは全く関係のない理由で訪問していました。今回、1回目の訪問時には、自然科学系のコースの説明や海藻の研究を行っているラボの見学、また私の専門である化学系のラボも見学することができました。2回目の訪問時には、Joondalupで有名なサイバーセキュリティーなどを扱う情報系のビルディングの見学をし、ロックがかかっていて普段は入ることができないようなセキュリティールームなどにも入ることができ、非常に興味深いものにたくさん触れることができました。昨年TAPで仲良くしていた友人の1人は情報科学部の学生なので、今回訪問に一緒に行く事ができていたら彼はさぞ喜んだことだろうと思います。最も印象的だったのは、2回目の訪問時にお会いした、非常にユーモアに溢れたIT分野の教授です。私たちにアソーテッドクッキーをプレゼントしてくれたり、突然訪れた授業中の教室で知らない学生に「今日は君が話をしてくれるんだよね?」と唐突に話しかけてみたり(その学生はただNOと言っていましたが笑)、帰りにエレベーター前でお別れしたのに、自分は非常階段で急いで降りてきて私たちの前にまた現れてお別れの挨拶をしてくれたりと、とても素敵なおもてなしをしてくれました。私たちは慣れない乗り換えで両日とも遅刻してしまいましたが、快く受け入れて案内をして頂いた先生方に感謝しています。
昨年、私はおよそ4ヶ月をパースで過ごし、後ろ髪を引かれる思いで帰国してきました。次一体いつ会えるかわからない友達とさよならをするのは非常に悲しいものでしたが、まさか自分が1年もしないうちにパースに戻ってくるなんて思いもしませんでした。私は今回パースに帰ってくるにあたり、パースにいるすべての友人に連絡をとり、できるだけ多くの友人と会う予定で忙しくしていました。ディナーをご馳走してくれたり、お家に招いてくれたり、車でさまざまな場所へ連れて行ってくれたりと、みんな私との再会を非常に喜び、素敵なおもてなしをしてくれました。現地に住む人のお家へ訪問すると、その家の大きさに驚愕することが多いです。昨年から仲良くさせていただいている、TAPのprogramofficerであるVeeさんのお宅に招いていただいた際には、とても美味しいシュニッツェルと自家製オリーブなどを頂き、ルームツアーもして頂いたのですが、驚くことに庭に巨大なトランポリンがあり、その庭の大きさは私の日本の家の1階と同じくらいの広さでした。しかし、彼女の親戚がシルビアから訪れると、シルビアではとても大きいお家に住んでいるそうなので、小さくて素敵なお家に招いてくれてありがとう、と言われるそうです。びっくりです。
私事ですが、私は誕生日が9月14日のため、2年続けて誕生日をパースで過ごすことになりました。昨年は私の部屋にルームメイトたちと日本人の友達をたくさん呼んでパーティーを行いましたが、今年は去年の面子で集まることは叶わなかったため、去年同じルームに住んでいたフラットメイトと彼女の親友が、一緒にレストランとケーキ屋さんに行ってお祝いしてくれました。友人たちから素敵なバースデープレゼントをもらい、忘れられない誕 生日になりました。
パースの街中にはさまざまな国の料理屋さんや、雑貨屋さんが多くあります。オーストラリアの約 4割は移民であると聞いたことがありますが、実際にパースにはさまざまな人種の人が住んでおり、たくさんの人が共に働いています。仕事をするにあたり、円滑にコミュニケーションを行い、業務を遂行することが不可欠ですが、パースではとりわけこの意識が高いように思います。違うバックグラウンドを持った人、違う言語を話す人、違う宗教信仰を持った人、違う食の好みを持った人が、一緒に生活していくには最低限相手の文化への理解が必要だからだと思います。日本は島国で単一民族国家のため、長い間異国間とのコミュニケーションを苦手としてきたように思います。私は見た目や学歴、性別や国籍で相手のことを判断するのがとても嫌いです。それは目の前にいる人の本質を見ておらず、外的要因だけで判断するのは相手に失礼だと思うからです。しかし、日本ではこのようなステレオタイプが多く存在していると思いますし、私はこのことを非常に残念に、悲しく思います。コロナ禍も過ぎ去ったことですし、もっと日本の学校や職場もインターナショナルになり、異文化交流が増えることで真の相互理解に努める人々が増えることを願っています。
長くなりましたが、私はこのプログラムに参加して本当によかったと思っています。TAPの時とはまた違う、より現地に近い生活を送ることで、さまざまな面でコアな部分に触れることができたと感じています。本来は今年の夏はインターンシップに参加し、院試勉強をしつつ、昨年参加できなかった合唱サークルの夏季合宿に参加して都大会コンクールに出場する予定でしたが、パイロットプログラムの募集を見て心が揺らいでしまったためchat GPTに相談してみました。そこで、他の項目についてはこの先もできるかもしれないが、 留学プログラムに関しては2度とないかもしれない貴重な機会だと助言を頂いたので、納得してパイロットプログラムに参加することを決めました。あの時chat GPTの助言がなければ私の夏休みは全く違うものになり、今回の経験はなかったもしれないと思うと、chat GPT様には感謝してもしきれません。
最後に、私の選択に理解と支援をしてくれた家族や友人、チャンスを与えてくれた大学と文科省に感謝したいと思います。ありがとうございました。