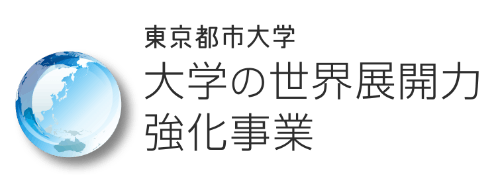JDパイロットプログラム派遣者レポート(2023年度派遣・5名)
JDパイロットプログラム レポート
環境学部 環境創生学科 2年 川口 桃瑚
オーストラリアでの6週間を通して、多くのことを学び自身の視野が広がった。日本にいるだけでは出会えなかった人、知らなかった文化と出会い、大学または大学院で学ぶとはどのようなことか考える機会を得た。大変なことも多くあったが、オーストラリアでの経験は私を色々な意味で成長させてくれた。様々な課外活動も行ったが、本プログラムでの学びや経験は主に3つに分けられる。それはSOARセッション、ジュンドラップキャンパスでのツアー、6週間の授業の3つである。
一つ目のSOARセッションでは、タイムマネジメントの方法、アプリを用いたデータ分析の方法、研究の流れなどについて学んだ。特に印象に残っているのは、最初のタイムマネジメントの方法と対面で行われたSOARセッションだ。前者では、①ゴールを設定すること②計画を立てること③モニタリングをすること④修正をすることが時間管理の主な軸であり、これらの実行が生活していく上でいかに重要かを学んだ。特にタスクを緊急度と重要度で整理するアイゼンハワーマトリクスは過去に一度取り組んだことがあったが挫折してしまったのでこれを機にまたはじめ、タスクの優先度が一目でわかるよう管理したいと思った。後者では、私たち学生3人に対し2人のアドバイザーが講義を行い、説明後には自分がこれから大学や大学院で研究を行っていくうえでこのセッションの内容がどんな風に生かせるかをディスカッションした。このセッションでは、研究に取り組む際にどのようにデータを集めるか、研究の際の定義付けや関係のある要素の特定をどのように行うか、担当の教授や各支援センターにどのようにサポートを受けるかなどを学んだ。これから研究室に入って研究に取り組む際に生かせる内容だった。私は環境分野を学んでいるが、倫理的な問題やステークホルダーなどに目を向けなくてはならないとセッション後のトークを通じて感じた。データ分析のセッションはデータや数学に関わる専門用語が多く、ついていくことで精一杯だった。最後のSOARセッションでは、前半はピアソンの相関係数とスピアマンの順位相関係数について学び、後半では回帰分析について学んだ。ある結果に関連する要因がどのくらい影響を与えているか、その因果関係を関数によって明らかにする手法を理解した。これらの統計学的手法は、研究を行う際やデータ収集をする際に役に立つと思う。
二つ目のジュンドラップキャンパスへのツアーでは、研究室訪問・ECUの大学院についての説明の聴講・キャンパスツアー・サイバーセキュリティの授業見学や施設訪問を行った。研究室訪問では、子どもの尿から持病を特定する研究、海藻の環境の変化による成長度の違いの研究を行っている研究室を訪問した。人の血ではなく尿から持病を持っている可能性を確かめられるというのは初めて聞いたので前者は特に興味深かった。特に二回目のサイバーセキュリティでは授業の様子を少しだけ見学させていただいたが、カリキュラムが実践的なものが多く設備も充実しておりとても魅力的だった。また、キャンパスがマウントローリー校と比較してとても広く、学生のための設備・イベント、研究環境が充実しておりとても魅力的に感じた。
三つ目の6週間のAE4での授業を通して、英語でエッセイを書く力、英語で情報をまとめる力、リスニングで大切な情報とそれ以外を区別して聞く力などが身に付いた。日本での勉強との違いは英語で英語を学ぶこと、英語力以外でいえばCritical thinkingだ。日本にいると日本語の文法書や日本語で意味が書かれている単語帳などを使って勉強をするが、オールイングリッシュでの勉強は、ネイティブスピーカーの先生から表現がフォーマルかカジュアルかなど細かいニュアンスを学ぶことができるのでとても勉強になった。また、後者のCritical thinkingは授業内でのディスカッションを通して学んだ。Critical thinkingとは物事の本質を見極めること、本当にそれが正しいのかを検討することだ。授業内のディスカッションでは、各々のテーマの背景やメリット・デメリットを考えた。また、クラスメイトのほとんどが異なる国からきた学生という環境なので、各々の育った国や置かれている環境が全く違いどの意見も興味深かった。日本で授業を受けていると、小学校から今まで先生が正しいとすることをそのまま受け入れなくてはならないといった風潮があるように感じる。しかし、ECUでの授業はそうではなく必ずディスカッションを通して自分の考えに客観性を持たせたり、本質を見極めたりする時間が多かった。模擬アセスメントで読んだ文章にもあったが、このCritical thinkingはオーストラリア全体で主流の教育手法であるそうだ。自分の考えを持ちそれに客観性を持たせ、他者と共有するオーストラリアの教育はとても魅力的で、また機会があればぜひこちらで勉強してみたいと思った。また、それ以外にはリサーチや文献引用の方法など大学や大学院で英語の論文を書く際の基礎も学んだ。文献引用の方法や、信頼できる情報の見極め方、そしてその情報や文献をどう自分の言葉に言い換えるかなど日本語でも学んだことがないことだったが、卒業論文を書く際や講義でのレポート課題に取り組む際に必ず生かすことができる内容だった。私はParaphrasing(言い換え)をせずにそのまま文献の記述を引用してしまったことがあるので、この授業はとても参考になった。英語での言い換えは少し難しいが、知っている語彙や言い回しを増やして伸ばしていきたい。
私は参加者5人の中では当初は一番英語ができなかったと思う。始めのうちは周りと自分の英語力をどうしても比べてしまい、自信をもてなかった。しかし今は、授業やクラスメイト・ホストマザーとの交流を通した自分の英語力の向上を実感している。記事の要約やリスニングエッセイは今までに取り組んだことがなかったので、返却された宿題は当初たくさん直しが入っていた。しかし、どこをどう直したらよいかをクラスメイトとお互いにアドバイスすることで同じ間違いを繰り返さないようになったり、例の要約と自分のものを比較することで正しい型が身についたりした。セミナーではグループの仲間と放課後に集まり交流をしたり準備を一緒に進めたりした。最終的には本番のリーディングアセスメントとセミナーでの発表で90%の成績を得ることができ、とても嬉しかった。苦手なこと・他者と比較して落ち込んでしまうことが、継続して努力することで実ったこの経験は私にとってすごく意味があり大切なことだ。これから先壁にぶつかることがあっても、この経験が必ず私の力になってくれるとそう思える。
私にとって大学院への進学、ましてや海外の大学院で学ぶことは私にとってすごくハードルの高いことであり、考えたことがほとんどなかった。しかし、このJDパイロットプログラムに参加したことで大学院への進学が卒業後の一つの選択肢になった。それには多くの理由があるが、5週間一緒に学んだクラスメイトの存在が大きい。日本にいると女性が結婚をして子供をもった後に大学や大学院で学ぶ・学びなおしをすることはとても挑戦的なことだとみなされる。しかし、パースでの私のクラスメイトはほとんどが30歳以上で、子どものいる母親も一緒に学んでいた。ホテル・レストランのマネージャーになるためにホスピタリティを、テクノロジーを駆使して働くためにサイバーセキュリティを学ぶ学生、自身の知見を広げ子どもたちにも高い教育を受けさせるためにパースに家族で移住してきた学生など、将来の夢や大学院で学びたいことが明確で、それについて話すクラスメイトがすごくまぶしく思えた。私も周りの友人たちもただぼんやりと将来について考えるだけで、何をこれからしたいか・どんな職業につきたいか明確なビジョンを持つ人は少ない。しかし、そんな素敵なクラスメイトとの交流が私に将来について考えるきっかけをくれた。また、もっと英語を勉強して海外の様々なバックグラウンドを持つ人と交流したい、一緒に勉強してみたいという気持ちにさせてくれた。このパースでの6週間で、自身の将来の選択肢や視野が広がり、新たに素敵な友人ができ、英語の勉強や将来について前向きな気持ちになった。帰国後も英語の勉強を継続して行っている。大変なこともあったが、本プログラムに参加できたことを心から嬉しく思う。